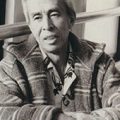『ハムレット』は、デンマークの王子ハムレットの復讐と苦悩を描くシェイクスピアの最高傑作です。本記事では、物語の全容、主要な登場人物の相関図、作品の成立背景、そして日本の舞台で変わる演出のポイントまで、ウェブで手軽に読めるよう網羅的に解説します。
近代的自我による復讐劇:『ハムレット』の基礎知識
1-1. 作品の基本情報と時代背景
『ハムレット』は1600年頃に執筆されたとされ、シェイクスピアの四大悲劇(『ハムレット』『オセロー』『リア王』『マクベス』)の一つに数えられます。
ジャンル: 悲劇(復讐劇)
舞台設定: デンマーク、エルシノア城とその周辺
テーマ: 復讐、生と死、狂気、人間の内省と行動
中世のデンマーク伝説を基に、ルネサンス期に隆盛した人文主義的な内省を深く加えることで、単なる復讐劇を超えた哲学的な作品となりました。
2. 【ネタバレ解説】『ハムレット』のあらすじ
デンマークの王子ハムレットは、父である国王の急死と、叔父クローディアスがすぐに王位を継ぎ母ガートルードと結婚したことに深い絶望を感じています。
2-1. 亡霊の告白と「狂気の芝居」の始まり
城の防壁で、ハムレットは父王の亡霊と出会い、亡霊からクローディアスによる毒殺の事実と復讐の命令を告げられます。ハムレットは復讐の真偽を探るため、「狂気」を装うようになります。彼は恋人オフィーリアへの態度も冷酷に変え、彼女を遠ざけます。
2-2. 「生きるべきか、死ぬべきか」の独白
ハムレットは、復讐という「行動」を起こすこと、そして「生」を続けることの苦悩に直面し、有名な独白を口にします。
「To be, or not to be, that is the question(生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ)」
この独白の後、ハムレットはオフィーリアを厳しく拒絶します。
2-3. 「生きるべきか、死ぬべきか」の独白
ハムレットは旅の一座に、父の殺害状況を再現した劇(劇中劇)を演じさせます。劇を見たクローディアスが激しく動揺したことから、ハムレットは叔父の有罪を確信します。その直後、ハムレットは母の部屋で、物陰に隠れて盗み聞きしていた侍従長ポローニアスを、クローディアスと誤認して刺殺してしまいます。
2-4. 追放と墓地での哲学的な対話
クローディアスは、ポローニアスを殺したハムレットを危険視し、イギリスへの追放を命じます。しかし、ハムレットは追放途中で船を襲った海賊の助けを得て、デンマークに生還します。
城へ戻る途中、彼は墓地で墓掘りに出会います。ハムレットは、掘り出された道化師ヨリックの頭蓋骨を手にし、誰もが最終的には死という平等に至るという哲学的な思索にふけります。
ハムレットはオフィーリアの葬列に遭遇。悲しみに打ちひしがれた兄レアーティーズは、妹の墓の上でハムレットと掴み合いになります。レアーティーズは父と妹の復讐を誓い、クローディアスと共謀してハムレットに剣での試合をすることになります。
2-4. 悲劇的な最期と王国の継承
城の中でレアーティーズとハムレットが試合を始めますが、これはクローディアスが仕組んだ罠で、レアーティーズの剣には毒が塗られ、勝利の杯にも毒が仕込まれていました。
試合の中、毒杯をガートルード王妃が誤って飲み死亡。ハムレットとレアーティーズも毒剣で傷を負います。死を悟ったハムレットは、レアーティーズを刺し、続いてクローディアスを討ち、ついに復讐を果たします。親友ホレーシオに真実を託し、ハムレットも息を引き取ります。最終的に、隣国ノルウェーのフォーティンブラス王子がデンマークの王位を継承します。
登場人物と相関図
| 登場人物 | 立場/関係 | 役割と特徴 |
|---|---|---|
| ハムレット | 主人公、デンマークの王子 | 思考を優先し、復讐を躊躇する「内省の人」。狂気を装う。 |
| クローディアス | 現国王、ハムレットの叔父 | 野心のために兄を毒殺した悪役。巧みな策謀家。 |
| ガートルード | 王妃、ハムレットの母 | 亡夫の死後すぐにクローディアスと再婚したことでハムレットから不信を抱かれる。 |
| オフィーリア | ポローニアスの娘、ハムレットの恋人 | 父と恋人の悲劇的な状況に巻き込まれ、正気を失い入水自殺する。 |
| ポローニアス | 侍従長 | 詮索好きで、ハムレットに刺殺される。 |
| レアーティーズ | ポローニアスの息子 | 妹と父の復讐に燃え、クローディアスと組んでハムレットを討とうとする。 |
舞台演出で変わる! 日本での翻訳版と省略される場面
省略されやすい場面
上演時間を短縮するため、特に以下の場面がカットまたは短縮されることがあります。
レアティーズのフランス帰還後の場面: レアーティーズの遊び人ぶりや、彼がクローディアスの陰謀に加担するまでの経緯に関する比較的長い会話。
旅役者との長い会話: 劇中劇の準備に関するハムレットと役者たちの技術的な議論や、演劇論に関するセリフ。
フォーティンブラス王子の登場: ノルウェーの王子フォーティンブラスの登場や、ポーランドへの侵攻に関する場面。彼の存在は、ハムレットの行動との対比(即断即決の行動力)を示す重要な要素ですが、物語の主軸から離れるため省略されやすいです。
演出の解釈で大きく変わるところ
演出家や俳優の解釈により、舞台の印象が大きく変化するのが『ハムレット』の醍醐味です。
ハムレットの「狂気」の解釈:
本当に精神を病んでいるのか、それとも復讐の計画のために完全に演技しているのか。演技として見せる場合、狂気の裏に冷徹な知性が感じられるように演じられます。
「生きるべきか、死ぬべきか」の独白:
この独白を自殺の可能性について語っていると解釈し、手に短剣やナイフを持っている場合。
あるいは、単に行動することの是非(復讐するかしないか)を哲学的に問うていると解釈する場合。
ガートルード王妃の関与:
夫(先王)の殺害について知っていた上でクローディアスと結託したのか、それとも無知で純粋に再婚しただけなのか。彼女の罪の意識の度合いによって、クローディアスとの関係性の見え方が変わります。
亡霊の存在:
亡霊が実際に現れたとして客観的に描かれるか、それともハムレットの**精神の産物(幻影)**として描かれるか。後者の場合、ハムレットの「狂気」の度合いがより強調されます。
翻訳版の選択とその影響
日本の舞台では、使用する翻訳版が作品の言葉の響き、テンポ、そして全体の雰囲気を決定づける非常に重要な要素となります。
福田恆存訳:
特徴: 荘重で格調高い文体。シェイクスピアのもつ古典的な重厚さ、悲劇の美しさを際立たせる傾向があります。伝統的な解釈や、重厚な悲劇として上演される際に選ばれやすいです。「To be, or not to be, that is the question」を「生か、死か、それが疑問だ」と訳しています。
小田島雄志訳:
特徴: 現代的で平易な言葉遣いとテンポの良さ。舞台上で俳優が話しやすく、観客にも内容が直感的に伝わりやすいのが利点です。現代的な解釈や、若々しくスピード感のある演出に使われやすいです。「To be, or not to be, that is the question」を「このままでいいのか、いけないのか、それが問題だ」と訳しました。
松岡和子訳:
特徴: 詩的なリズムを保ちつつ、女性的な視点や現代的な感覚を取り入れた言葉選び。詩的表現の美しさと、よりニュートラルで新しい解釈を可能にしています。「To be, or not to be, that is the question」を「生きてとどまるか、消えてなくなるか、それが問題だ」としました。
河合祥一郎訳:
特徴: 原典の詩的なリズムと、シェイクスピアが多用した言葉遊びや駄洒落を忠実に再現しようとするアプローチが特徴です。知的でウィットに富んだハムレット像を強調する演出で採用されることが多いです。「To be, or not to be, that is the question」を「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ」というもっとも広く知られる訳を採用しています。
演出家は、目指す作品のトーン(古風で重々しいか、現代的でテンポが良いか)に応じて、これらの翻訳版、あるいは他の翻訳家によるものを使い分けます。
なぜ数多く上演されるのか?
『ハムレット』は単なる復讐劇ではなく、人間の本質的な問いを投げかけ続ける永遠の傑作です。時代や演出家が変わるたびに新しい解釈が生まれるこの作品は、観客に深い感動と考察の機会を与え続けています。
ハムレットを映像で見る